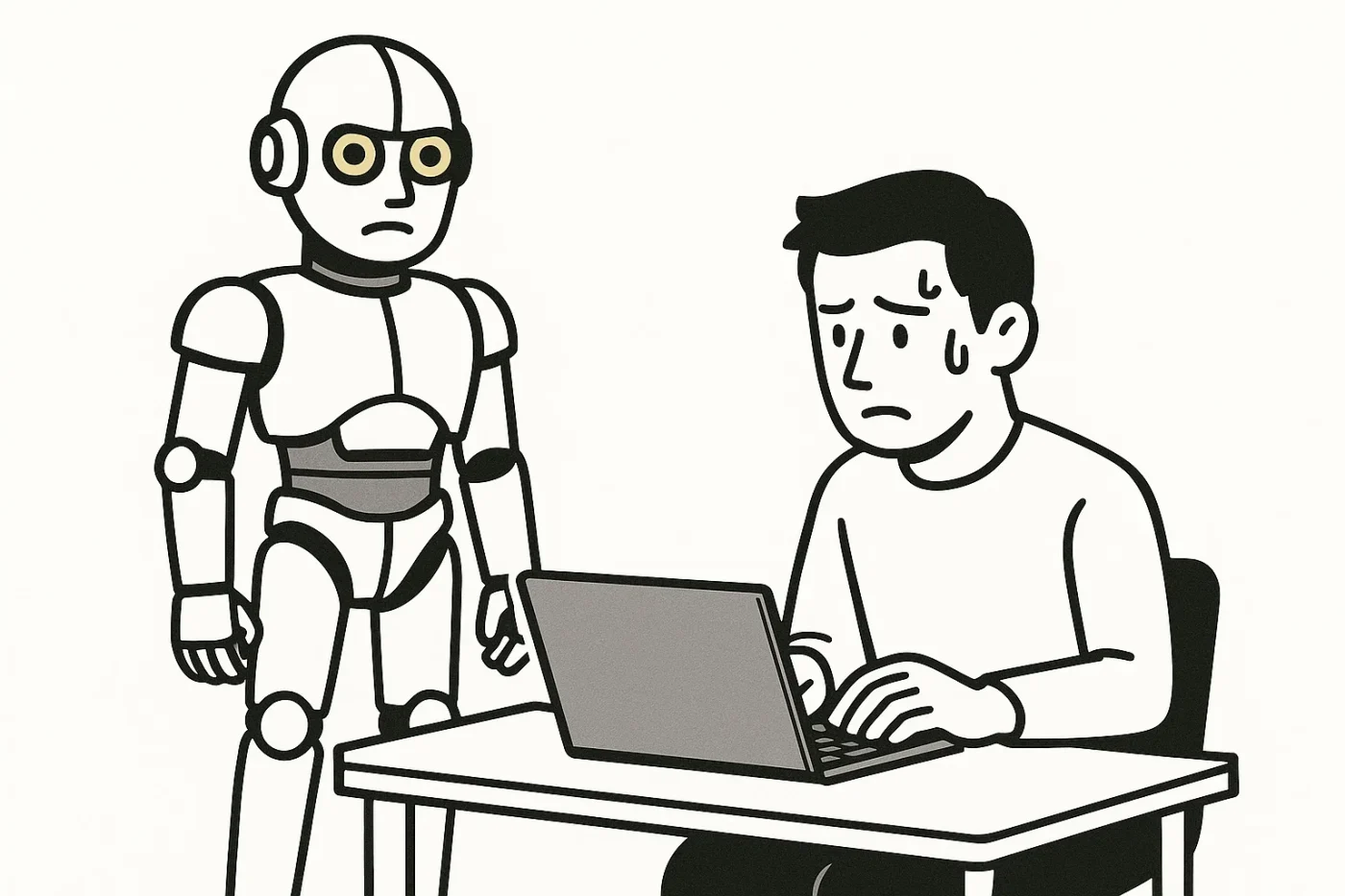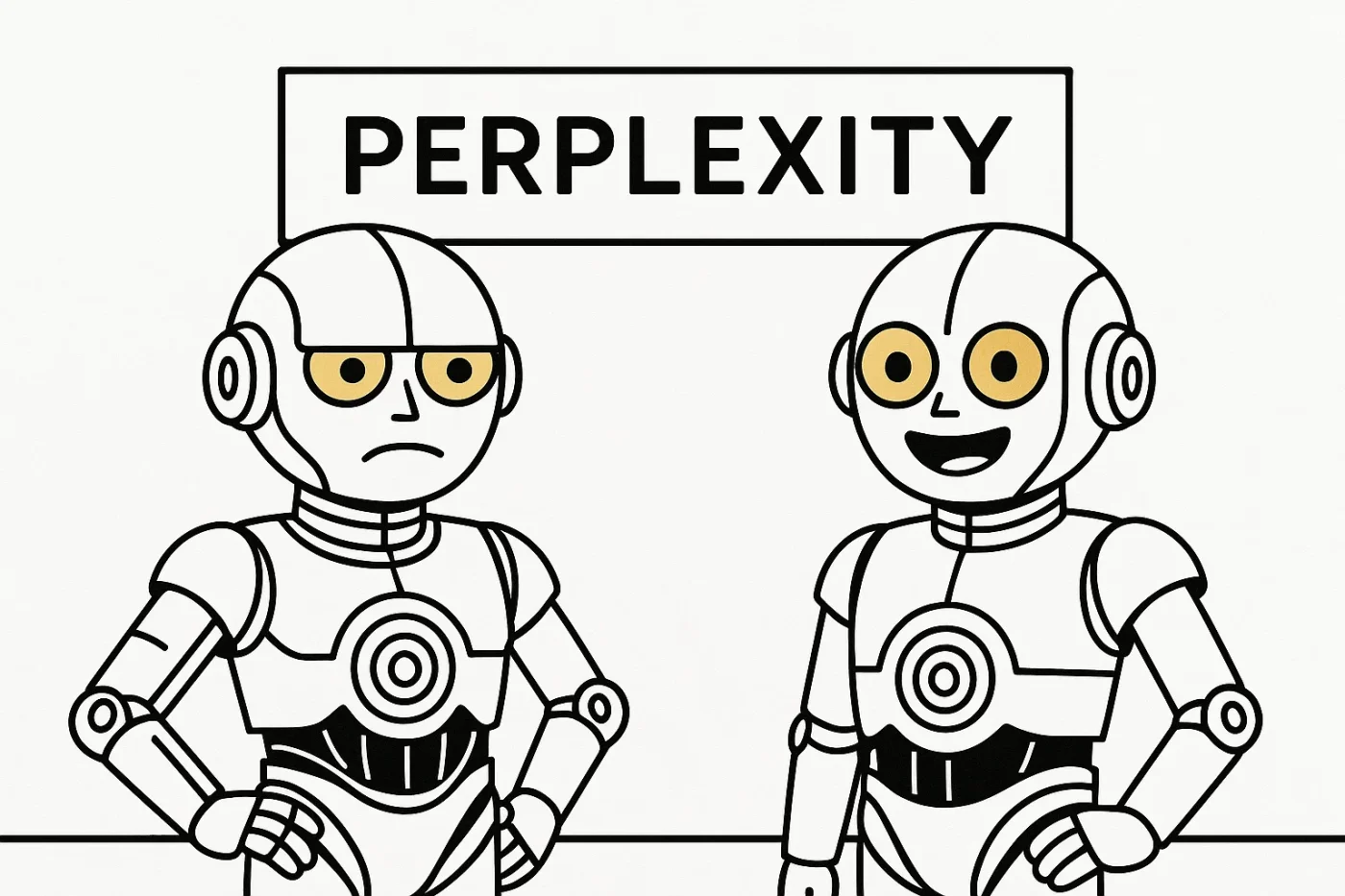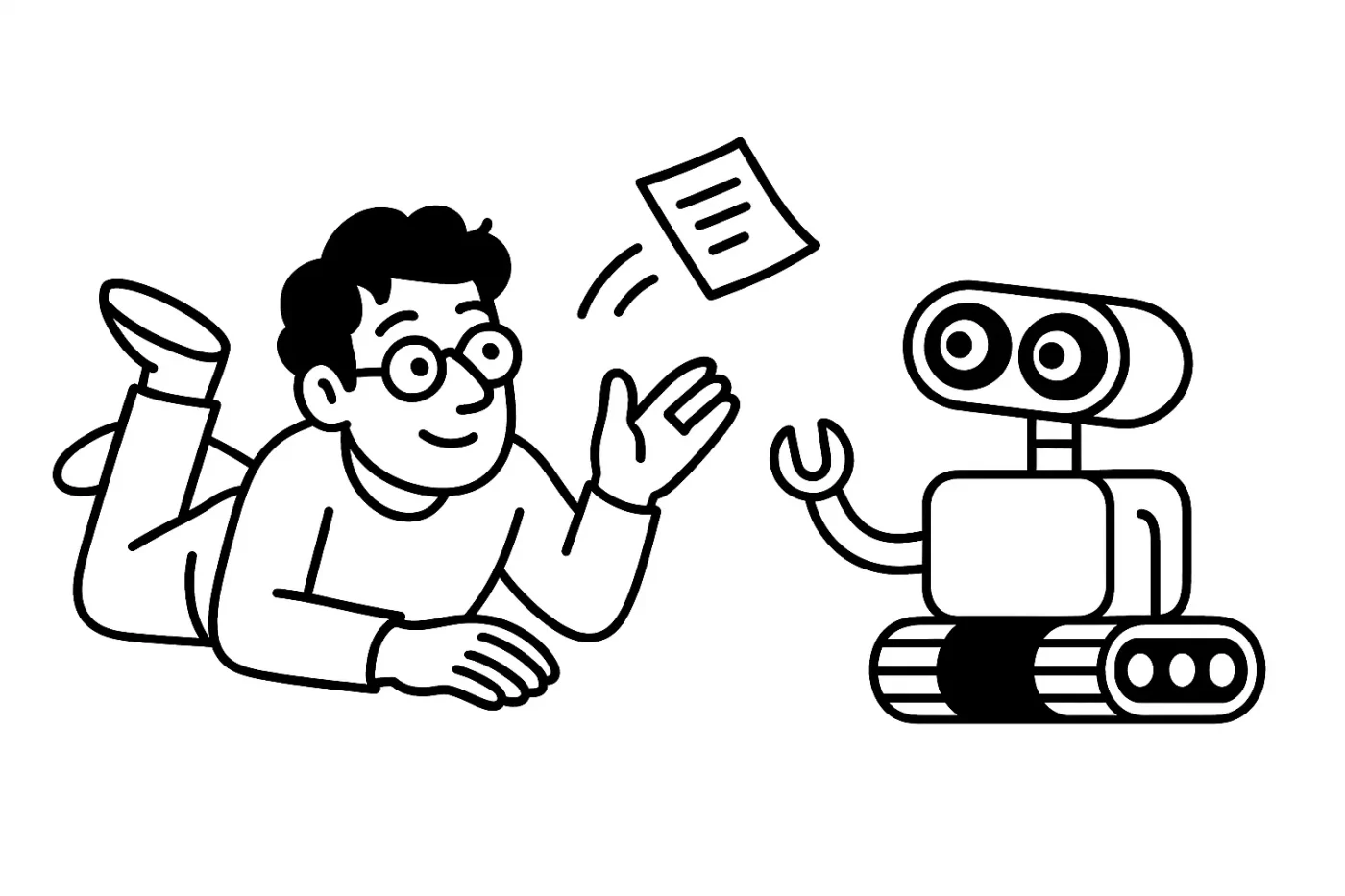「忖度なしで本音を聞かせて」
この一言で、いつも丁寧なPerplexityが急に辛辣な評論家に変身するのである。
紳士的Perplexity(通常モード)
普段のPerplexityは、まさに検索界の紳士である。
「この記事企画は非常に価値がある。読者にとって実用的で、SEO的にも効果が期待できるだろう。参考トピック例として…」 丁寧で建設的だ。
まるで優秀なコンサルタントのように、箇条書きで整理された提案を返してくれる。
豹変の瞬間
ところが「忖度なしで」という魔法の言葉を唱えた途端…
「正直に言うと、この記事はよくある啓蒙記事の域を出ていません」
「市場が飽和している感が正直なところです」
「率直に言って、今のままだと『ふーん』で終わってしまう記事です」
何この豹変ぶり!
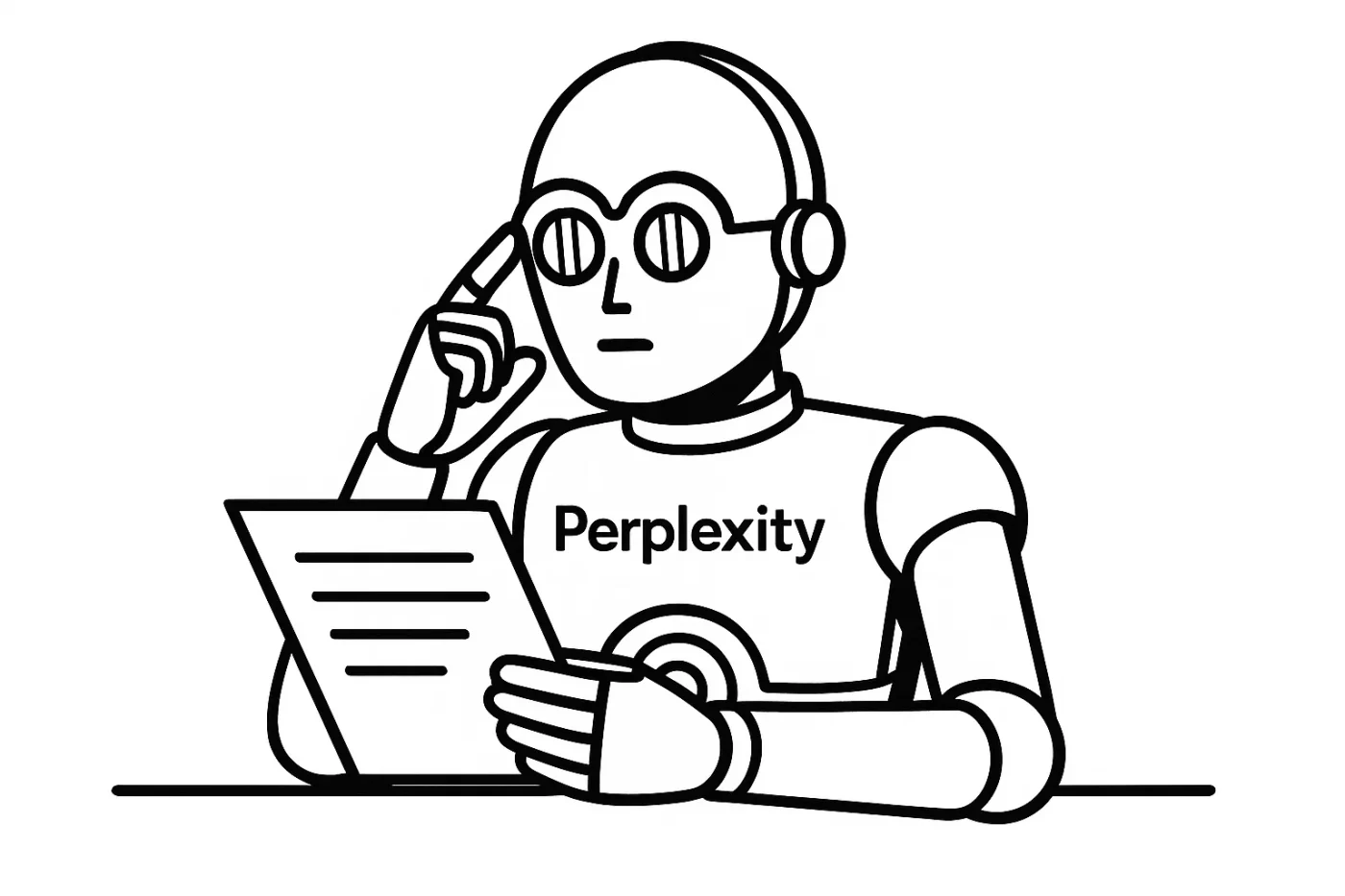
なぜこんなに変わるのか?
この現象の正体は、AIの学習データに含まれる多様な表現パターンにある。
「忖度なしで」というキーワードが、より直接的で批判的な表現を含むデータセットを呼び起こすトリガーとして機能するのである。
つまりPerplexityは:
- 建設的な議論パターン
- 率直な批評パターン
- 専門的な分析パターン
など、複数の「キャラクター」を内蔵していて、プロンプト次第で使い分けているということである。
他のAIとの比較
面白いことに、同じ「忖度なし」でも、AIによって反応が全然違う:
- Gemini: 「でも素晴らしい記事である」(絶対に傷つけない優しいお母さん)
- GPT: 「改善余地があるが、良い記事である」(建設的な小学校の先生)
- Claude: 「論理の飛躍がある」(容赦ない大学教授)
- Perplexity: 「よくある記事である」(市場分析する辛辣コンサル)
実用的な活用法
この「性格の使い分け」を理解すると、AIとのコミュニケーションが劇的に改善する:
建設的な意見が欲しいとき: 「〜について教えてください」
率直な評価が欲しいとき: 「忖度なしで本音を聞かせてください」
専門的な分析が欲しいとき: 「専門家の視点で詳しく解説してください」
まとめ
Perplexityの豹変は、単なる面白い現象ではない。
これはAIが持つ多面的な応答能力の表れであり、私たちがより効果的にAIを活用するためのヒントなのである。
次回Perplexityを使うときは、「どの顔」に話しかけたいのかを意識してみるとよい。
きっと、より豊かなAI体験ができるはずである。
関連リンク