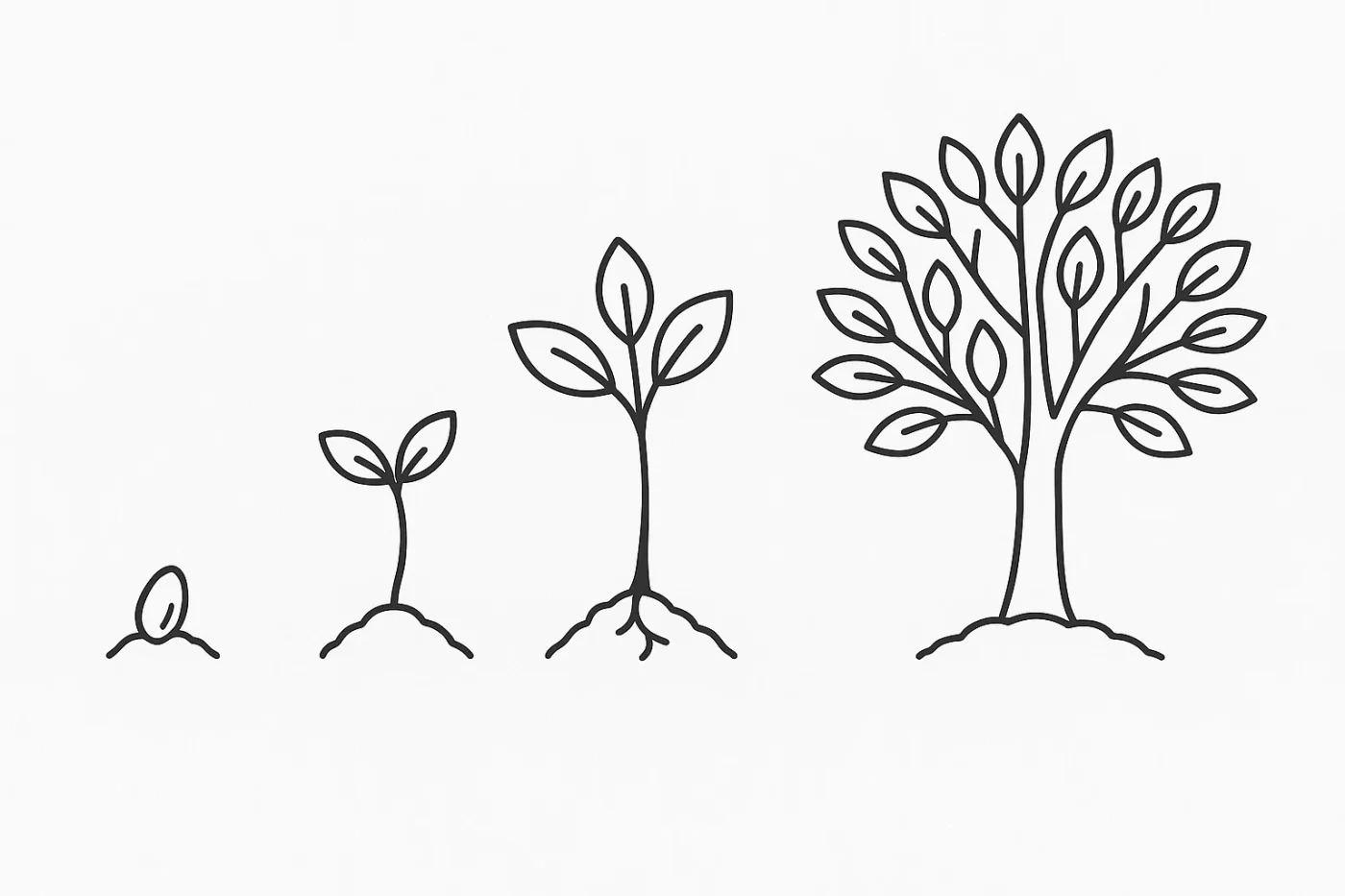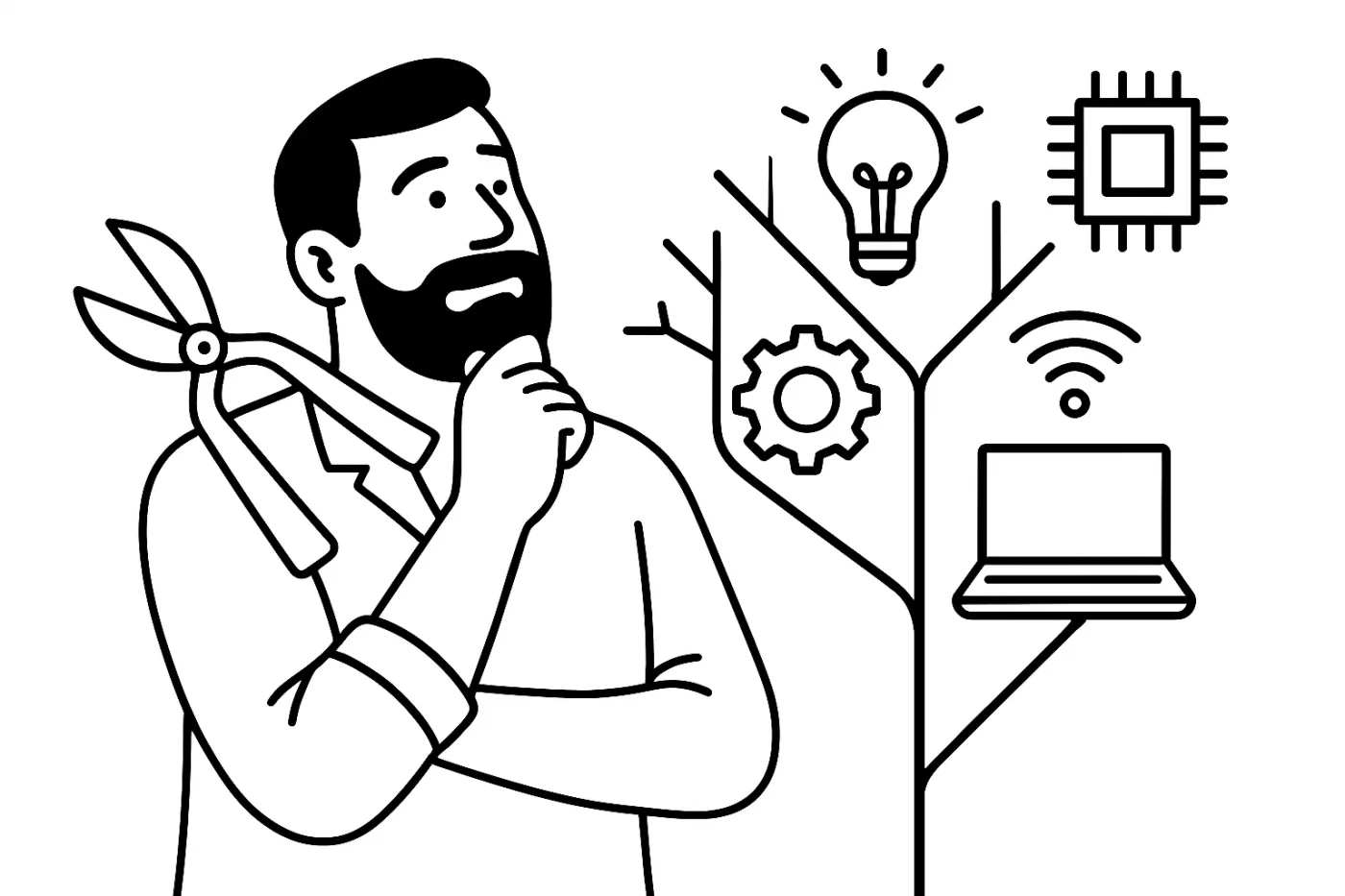第一幕「岐路に立つ男」
「社長、新規事業の企画書ができました」
取締役の田中が分厚い資料を机に置いた。表紙には「AI活用新サービス構想」と書かれている。
「また新規事業か…」
東京下町で製造業を営む中央精密の社長・山田太郎(52)は、深いため息をついた。32歳で先代から会社を継ぎ、従業員50名の会社を20年間守り抜いてきた男の顔に、疲労の色が濃い。
「でも社長、このままじゃジリ貧ですよ。大手との価格競争は限界です」
田中の言葉に、山田は窓の外を見つめた。工場の煙突から立ち上る白い煙が、秋空に溶けていく。
「発芽か、剪定か…」
山田がつぶやいた言葉に、田中は首をかしげた。
第二幕「コンサルタントの登場」
翌週、経営コンサルタントの佐藤が会社を訪れた。40代前半、鋭い目つきの男だ。
「山田社長、率直に申し上げます。御社は『発芽病』にかかっています」
「発芽病?」
「新しいことばかり考えて、既存事業の改善を怠る病気です。過去3年で5つの新規事業を立ち上げましたが、どれも中途半端でしょう?」
山田は苦笑いを浮かべた。図星だった。
「一方で」佐藤は続けた「既存の主力製品は10年間、基本設計が変わっていない。お客様のニーズは変化しているのに、です」
「つまり…?」
「今必要なのは剪定です。不採算事業を切り、主力に集中する。そして主力事業に新しい芽を出させるんです」
第三幕「決断の時」
役員会議。重苦しい空気が会議室を支配していた。
「5つの新規事業のうち、3つを撤退します」
山田の発言に、役員たちがざわめいた。
「社長、せっかく育ててきた事業を…」
「育ててない!」山田の声が響いた。「中途半端に手を出して、どれも花を咲かせていない。これが現実だ」
営業部長の鈴木が反論した。
「でも将来性のある分野もあります。AI事業なんて…」
「鈴木さん」山田は静かに言った「植物を育てたことはありますか?」
「え?」
「剪定をしないと、栄養が分散して、どの枝も貧弱になる。でも思い切って切ると、残った枝に力が集中して、見事な花を咲かせるんです」
第四幕「剪定の痛み」
撤退決定から3ヶ月。リストラは避けたものの、担当者たちの落胆は隠せなかった。
「俺たちの3年間は何だったんだ…」
AI事業の責任者だった若手の田村がつぶやく。
山田は田村を呼んだ。
「田村君、君のAIの知識を主力事業に活かしてもらいたい」
「え?」
「製造工程の改善にAIを使えないか?お客様の要求仕様の分析にAIを活用できないか?新規事業で培った技術を、既存事業で花開かせるんだ」
田村の目に光が戻った。
第五幕「新しい芽」
1年後。中央精密の主力製品に革命が起きていた。
AIを活用した品質管理システム、顧客ニーズを先読みする受注システム。従来の製造業の枠を超えた付加価値サービスが次々と生まれた。
「社長、大手A社から専属契約の打診です」
田中が興奮気味に報告した。
「価格は従来の1.5倍。技術力を評価しての提案です」
山田は微笑んだ。
「発芽と剪定、両方必要だったんだな」
エピローグ「真の両利きの経営」
事業が安定した頃、山田は佐藤に言った。
「発芽プロジェクトと剪定能力、どちらも大切ですね」
「そうです。でも順番とタイミングが重要です」佐藤は答えた。
「まず剪定で既存事業を強化し、その利益で新しい発芽に投資する。そして発芽した事業が育ったら、また剪定で選択と集中。このサイクルが大切なんです」
山田は工場を見渡した。効率化された生産ライン、新技術を学ぶ従業員たち、そして隣の空きスペースには、次世代製品の試作機が置かれていた。
「発芽と剪定。植物の成長と同じだな」
山田がつぶやくと、佐藤は頷いた。
「経営も自然の摂理に従うということですね、山田社長」
【BOSS’s View】
この物語は架空ですが、多くの中小企業が直面する現実でもあります。新規事業への希望と、既存事業の改善。どちらも重要ですが、タイミングと順序を間違えると共倒れになります。
真の「両利きの経営」とは、闇雲に両方やることではない。強い幹があってこそ、新しい枝も育つのです。
あなたの会社は今、発芽の時ですか?それとも剪定の時ですか?
関連リンク