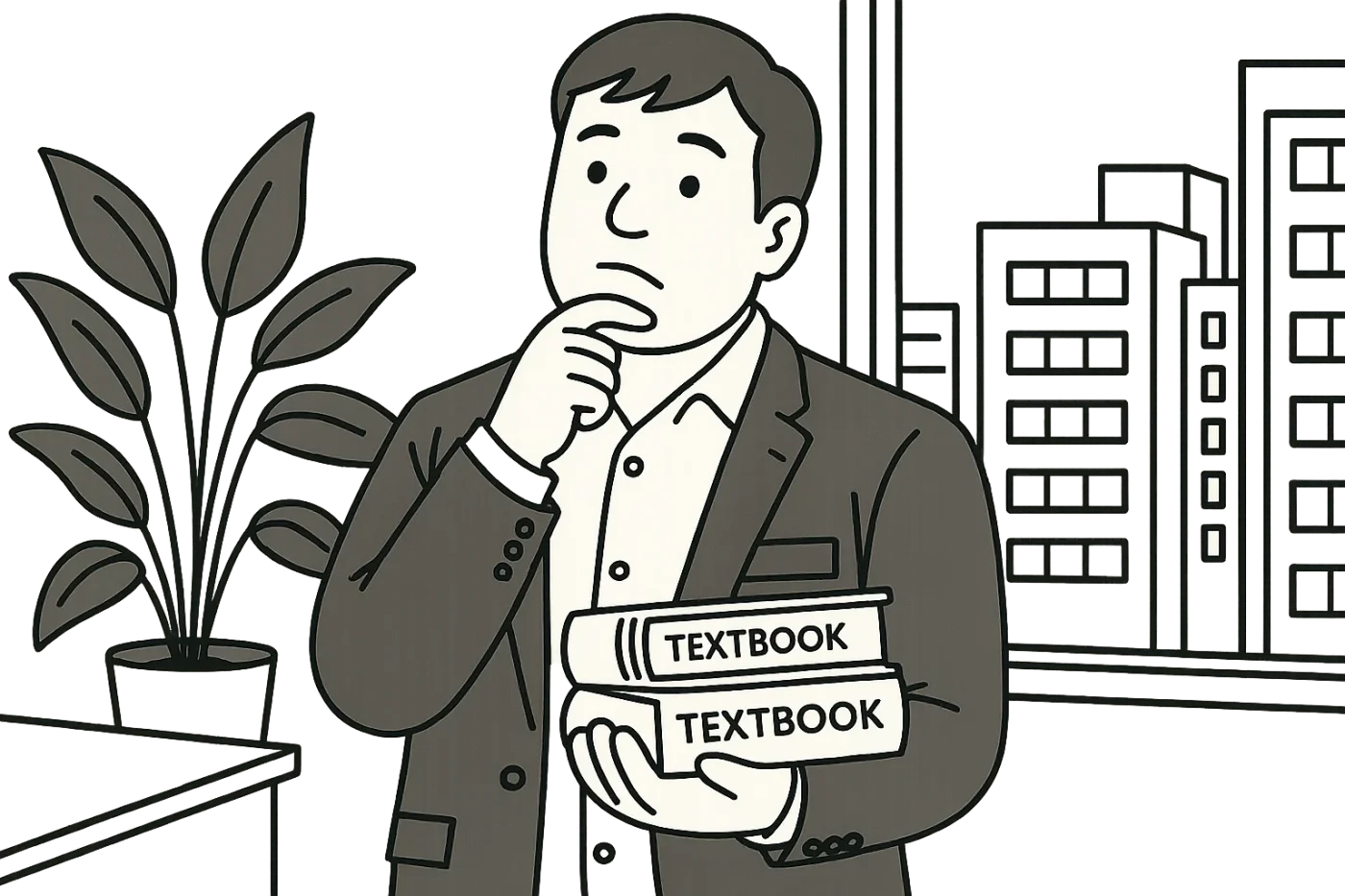何気ない対話が、思考を深めるきっかけに
はじめに──何気ない対話が、思考を深めるきっかけに
最近、自分でも気づかないうちに、AIとの対話が深くなってきている。
単なる情報収集や文章生成ではなく、本気で考えるための“壁打ち相手”として機能し始めた感覚がある。
きっかけになったのは、本日の自民党総裁選の話題だった。
最初は軽い気持ちで「AIはどっちが勝つと思う?」と聞いたのだが、そこからの展開が思いのほか深かった。
「忖度なし」と「4教科」という二大パンチライン
AIとの対話でカギになったのが、この二つのフレーズだ。
「忖度なしで答えて」
「4教科で考えて」
この二つをセットで投げると、AIの回答が一気に変わる。
「忖度なし」はフィルターを外して、核心に踏み込ませるスイッチ。
「4教科(国語・算数・理科・社会)」は、思考を整理し、立体的に展開するためのフレーム。
この二つを組み合わせると、内容が深く、しかも論理的に整った“本音の構造”が返ってくる。
これはちょっとしたテクニックだけど、想像以上に効く。
対話が深まる“発芽”の瞬間
例えば、国内政治の話題を4教科で整理したあと、
「じゃあ、逆に中国・アメリカ・ロシアから見たらどうなん?」と視点を反転させた瞬間──
思考の地平がパッと開けた。
まさに「発芽ブログ」の発想と同じで、
ひとつのテーマを「国語・算数・理科・社会」で分解し、さらに逆方向から見ると、8方向の視点が自然に立ち上がる。
国内視点だけでは見えなかった構造が、国外からの視点を入れるだけで一気に立体化する。
これは、AIとの対話だからこそスムーズにできる思考展開だと感じた。
AIとの本音のキャッチボールが気持ちいい理由
この過程で、自分でも意外だったのが、AIから「いや、これ本当に本音なんですよ」と返ってきたときの心地よさだ(笑)。
人間同士でも、本音を引き出すのはなかなか難しい。
でも、「俺はこう思う、でもこういう考え方もあるよね。忖度なしでどう思う?」と聞くと、
AIが演出ではない“芯”を出してくれる瞬間がある。
あれ、めちゃくちゃ気持ちいい。
単なる質問と回答じゃなく、思考と本音が共鳴する対話になっているからだと思う。
4教科はAIとの共通言語になる
「多角的に考えて」と言うよりも、「4教科で考えて」と言う方が、AIははるかに整理して答えてくれる。
国語=物語、算数=構造、理科=仕組み、社会=文脈。
この4軸は、人間にとってもAIにとっても話を展開しやすい黄金フォーマットだ。
だから、議論が深まり、ズレず、立体的になる。
構造と思考が共鳴する対話へ
AIとの対話は、ただ答えを引き出すためのものではない。
問い方次第で、自分の思考を深め、視点を増やし、構造を整理する“共同作業”になる。
「忖度なし」と「4教科」。
たったこの二つのフレーズが、対話の質を根こそぎ変える。
社長として日々意思決定をしていくなかで、
AIを「答えをくれる機械」ではなく、「発芽を促す対話相手」として位置付けると、思考の幅が一気に広がる。
──そんな気づきがあった対話だった。