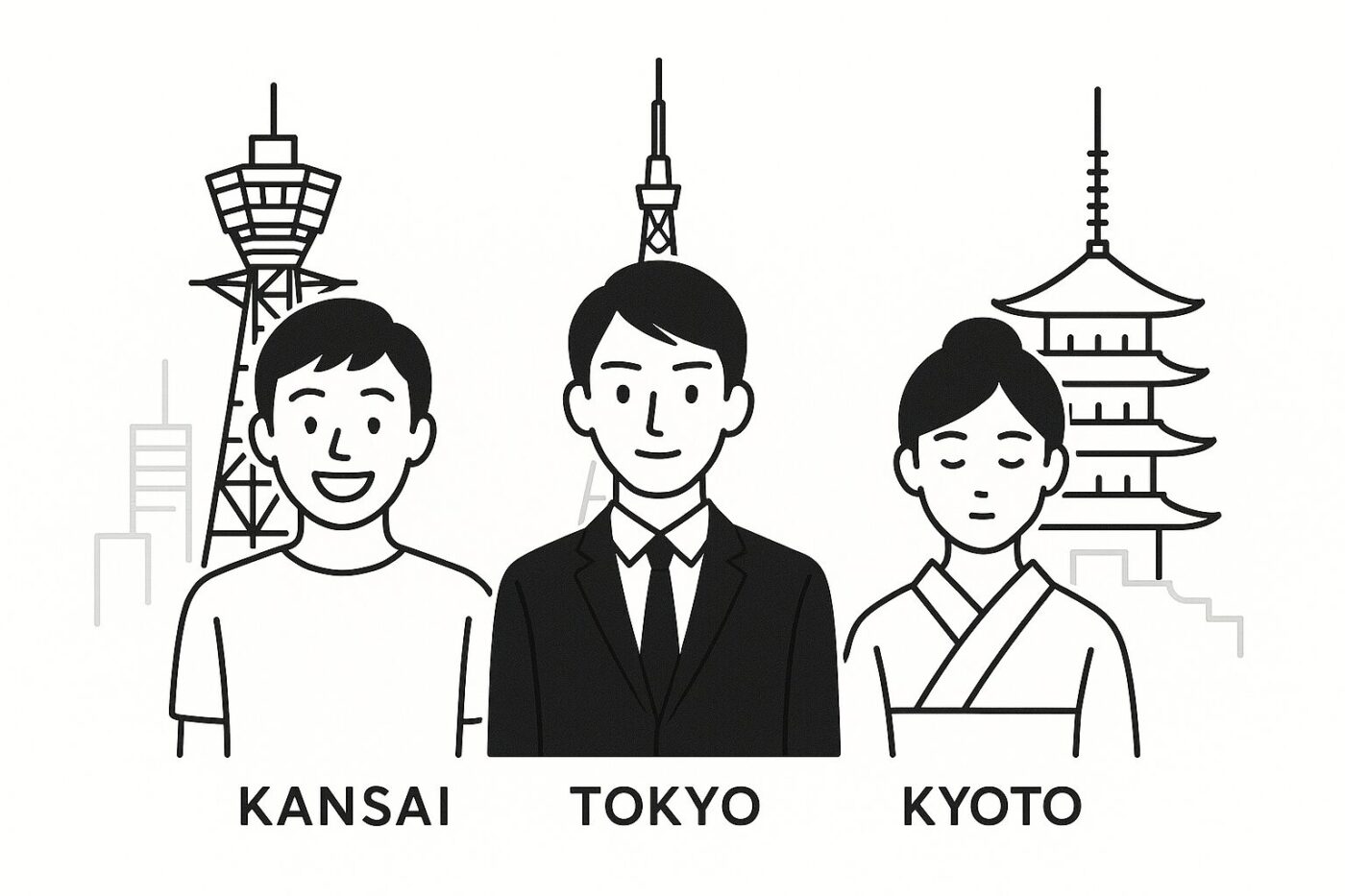“京都人やなぁ”と思ってしまう瞬間
最近ふと気づいた。
「関西人は嫌い」「東京人はいけすかん」──
そんな言葉を、もうほとんど聞かなくなった。
でもなぜか、「京都人やなぁ」とは、いまだに思ってしまう。
いい意味でも、悪い意味でも。
どうしてなんだろう。
ステレオタイプが消えた時代
昔は「関西vs東京」という対立構図が、笑いのネタとしてよく機能していた。
ボケとツッコミ、ノリと冷静、派手とクール。
けれど今はSNSでどの地域の人ともリアルタイムに関われる。
だから“東京人”“関西人”というラベル自体が、
あまり意味を持たなくなったのかもしれない。
他者を笑うよりも、自分の好きなことを語る時代。
文化は対立よりも、発信の方向へ変わっていった。
京都人が残る理由
それでも「京都人」だけは、どこか特別な響きを持つ。
おそらくそれは、京都という街が“千年の文脈”を背負っているからだろう。
言葉の奥にある間合い、婉曲な表現、空気を読む知性。
京都人を見るとき、僕らは無意識に「歴史の厚み」と向き合っている。
だからこそ、尊敬と警戒が半分ずつ混ざる。
それが「京都人やなぁ」の本当の意味だと思う。
成熟とは、違いを距離で扱えること
関西・東京・京都。
この三つの文化圏は、かつて競い合っていた。
でも今は、たがいに“踏み込みすぎない”関係になっている。
それは冷たさではなく、成熟のサインだ。
違いを笑うのではなく、
違いを保ったまま共存する。
それが、大人になった社会の姿なのかもしれない。